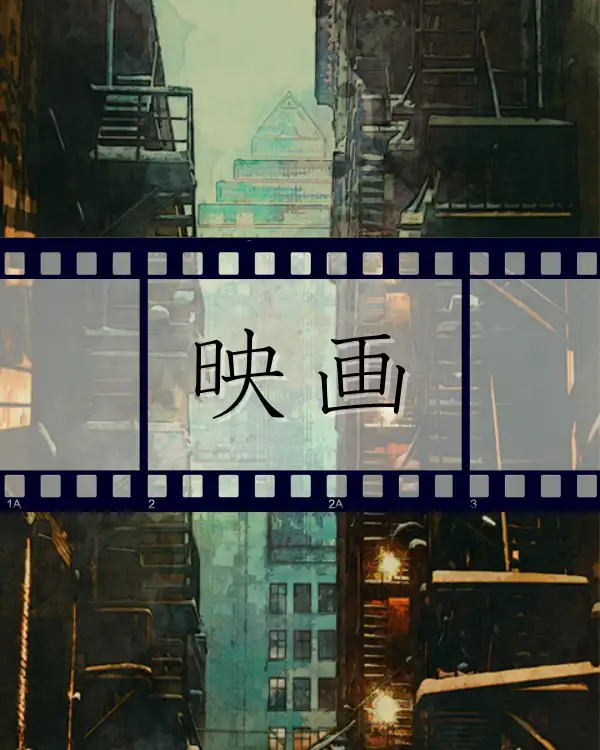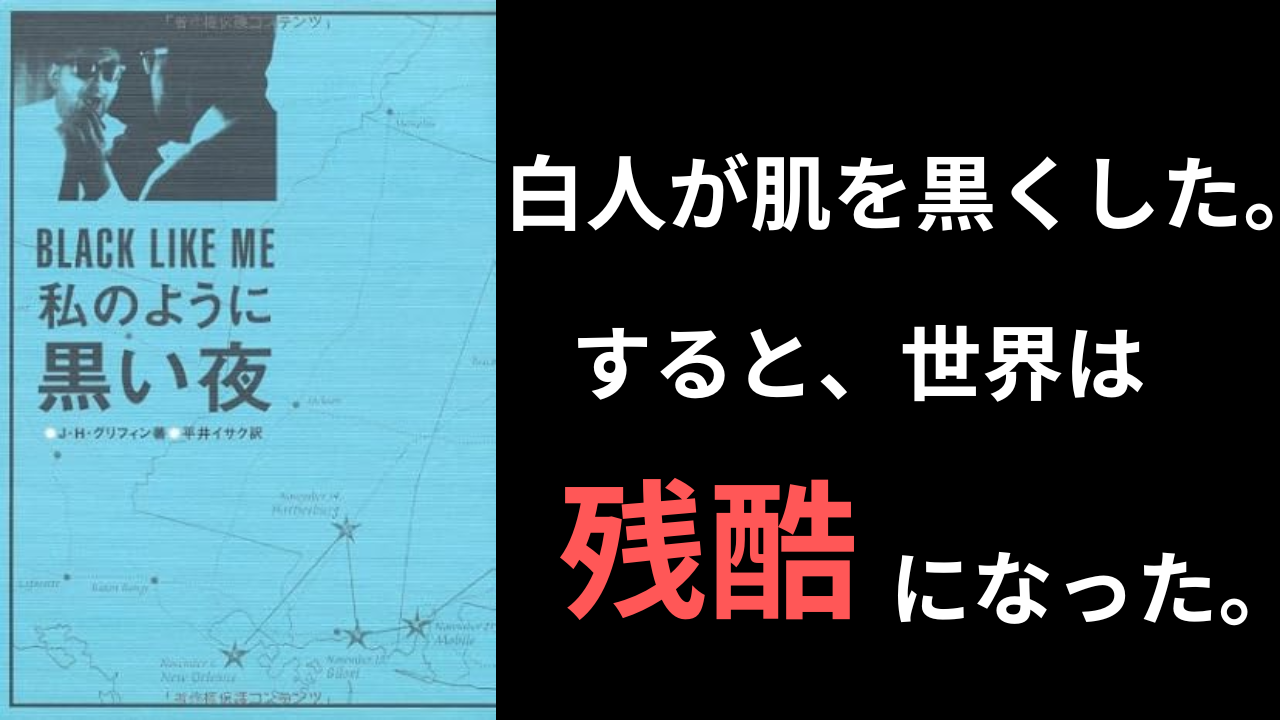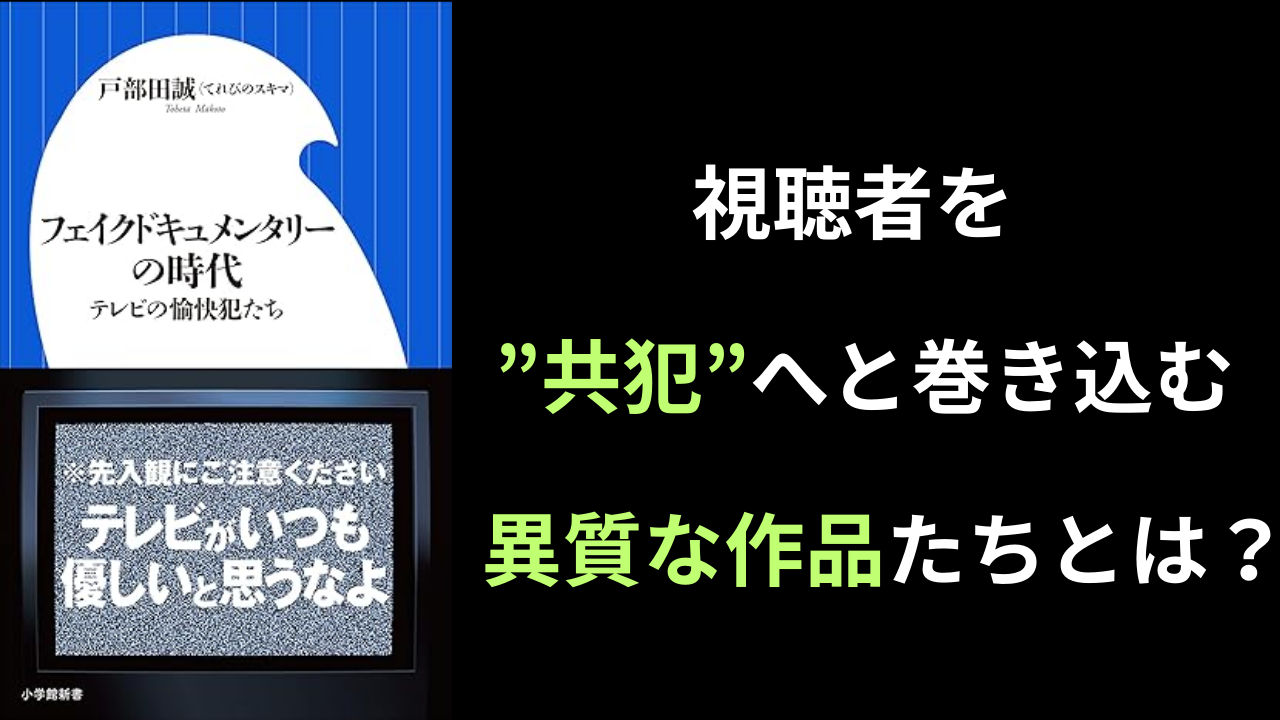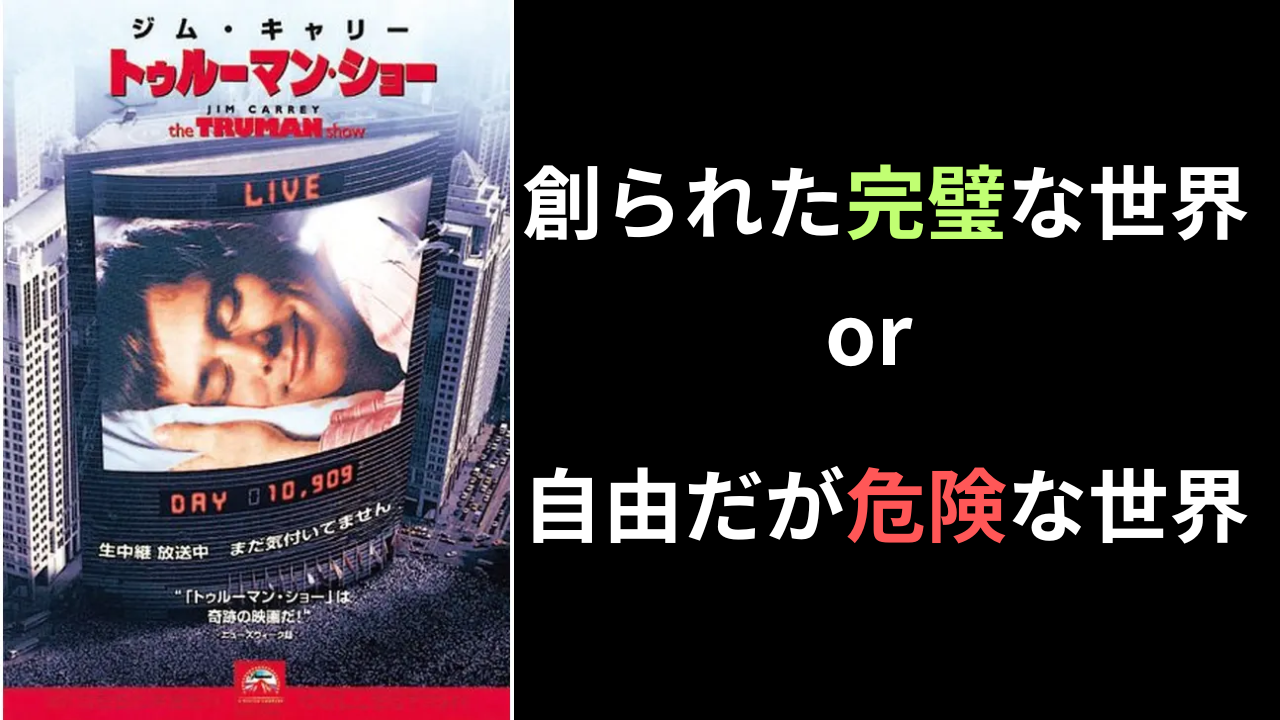1959年アメリカ合衆国、命を脅かすほどの黒人差別が暗黙のうちに認められていた時代。闇に閉ざされた実態を明らかにするため、全身を黒く変色させ、米国南部へ潜入した白人ジャーナリストがいた。戦争による盲目、そして光を突然とり戻すという数奇を体験した白人グリフィンがそこで得た真実は?当時、世界に衝撃を与えた“南部の旅”日記に、その後の余波、著者の経歴を含むあとがき等が大幅加筆。今尚、アメリカのあり方を深く問い続ける名著、平井イサク名訳(全面改訳)により、待望の復刻。(Amazon『私のように黒い夜 』より引用)
全身を黒くした白人男性が、内側から黒人差別を覗き込む
一番の衝撃は、この本がノンフィクションであることだ。薬物治療によって皮膚を黒く染めた白人男性も、黒人には白人女性を見ることすら許されないといった差別も、現実に存在していた。
1959年のアメリカには、依然として黒人差別が存在していた。南部の州議員たちは黒人と「すばらしくうまくいっている」と言っているが、そんなのはあまりにも見え透いた嘘だった。筆者のグリフィンは、「黒人になる以外、差別の真相を知ることはできない」として、黒人になることを決意した。
グリフィンは治療によって一ヶ月ほど黒人として生活することになった。黒人差別の実情は果たしてどのようなものなのか。想像を絶する酷さなのか。それとも州議員の言うように、存外穏やかなものなのか。
皮膚の色が変わっても、自分は自分。周囲の人びとの目は変わらない。そんな甘い幻想は、はなから否定されていた。
「皮膚の色に関係なく、ジョン・ハワード・グリフィンとして、僕を扱ってくれると思いますか――それとも、僕は前と同じ人間なのに、名もない黒人として扱われると思いますか?」と、私は訊いた。
「冗談いっちゃいけませんよ」と、捜査官の一人がいった。「連中は何一つ訊かないでしょうね。あなたを見たとたんに、黒人だと思い、それさえわかれば、他のことは何一つ知りたいとも思いませんよ」(『私のように黒い夜 』p.15)
黒人には”黒人”というアイデンティティしか認められていない。連邦捜査局の捜査官はそうグリフィンに警告する。
そして、実際にグリフィンが内側から見た差別の実態は、とてもおぞましいものだった。
白人女性を見ることすら許されない
黒い皮膚になった途端、グリフィンを取り囲む世界は一変した。白人である自分に対しては、世の多くの白人男性は紳士的で柔和な笑顔をまとっていた。しかし、”黒人”の自分に向けられるのは軽蔑と好奇の目だけであった。
上品な顔立ちをした女性は青筋を立てて怒鳴り散らし、紳士然とした男性は”黒人は千変万化の性経験を持つセックス・マシーン”という伝説を信じて根掘り葉掘り聞いてくる。それらはグリフィンが白人であった頃にはとても考えられない光景だった。
グリフィンがミシシッピを訪れた時、親切な黒人は彼にこう忠告した。
「とにかく、白人の女には、目を向けてもいけないんだ。下を向くか、反対の方を向くようにするんだ」(中略)
「映画館の前を通って、外に女のポスターが出てたら、それも見ちゃいけないんだ」
「そこまで酷いのか?」
彼はそう断言した。別の男がいった。「必ず誰かが声をかけるよ――おい、ボーイ、どうしてそんな目で白人の女を見てるんだ、ってね」(『私のように黒い夜 』p.97)
黒人は、白人女性を見ることも許されない。街中には”黒人用”という表記のトイレや座席に溢れ、バスに乗ったら降ろしてもらえず、職を求める女性には身体を要求して「お前たちの子どもに白人の血を分けてやってる」と言い放つ。当時のアメリカ南部ではそんな差別が公然と行われていた。
日常化している白人による黒人差別。もちろんそれ自体問題であるが、この人種差別という問題の深刻性は別なところにも潜んでいる。それは、黒人自身による自己疎外である。
「黒人にとって運命とはただ一つしかない」『黒い皮膚・白い仮面』
グリフィンは”実験”のかなり早い段階から黒人の自己疎外という問題に気づいていた。彼は”仲間”の黒人たちと語り合う中で、黒人には二重の問題があると彼らが認めていることを知った。
第一の問題は、黒人に対する白人の差別。第二の、より嘆かわしいといってもいいような問題は、黒人の黒人自身に対する差別。苦しみを思い起こさせる黒いということに対する、黒人自身の軽蔑。彼自身がそのためにさんざん苦しんできた<黒>の一部であるが故に、仲間の黒人の足を引っ張ってやろうという気持ち。(『私のように黒い夜 』p.71)
差別は内面化する。“白人優位、黒人劣位”という支配的な植民地文化に慣れすぎたために、自らの黒い肌に自分から軽蔑の目を向けるようになってしまったのだ。
こうした黒人の自己疎外について、哲学者にして精神科医であったフランツ・ファノンは『黒い皮膚・白い仮面』で精緻な分析を行っている。
その著書の中で、ファノンは「それがどんなに辛いことであれ、次の点を確認せざるをえない。」と前置きし、次のように述べている。
黒人にとって運命はただ一つしかない、ということ。その運命とは白人である。(『黒い皮膚・白い仮面』p.33)
黒人の運命は白人しかない。そのファノンの言葉の意味を説明する。
ヨーロッパの植民地文化は、”黒人である”ことを不純であることと同一視する傾向があった。植民地の規則に服従させられた人々はこの認識を受け入れ、自分たちの肌の色を劣等のしるしとみなすようになった。植民地化された人々は、この”不純”という立場から脱することを願う。そのための唯一の手段は”黒人であること”を拒否することであり、すなわち”白人になること”なのだ。
ファノンの主張は続く。この白人になるという“白い実存”は実現しない。肌が黒いという事実は変えられないからだ。さらに、”白い実存”を実現したいという願いは、白人の優位を認めるものであり、人種差別や不平等という問題を覆ってしまいさえするのだ。
黒人の不幸は奴隷化されたということである。
白人の不幸と非人間性はどこかで人間を殺してしまったということである。(『黒い皮膚・白い仮面』p.249)
黒人差別にまつわる不幸は、かつて植民地化されてしまったという歴史的事実ただそれのみに起因する。では、この問題はどうやって乗り越えられるか?
二項対立を乗り越える
白人化を目指す”白い実存”。あるいは黒人の優越性を説く”ネグリチュード”。どちらも黒人が差別から脱するために生まれた。
しかし、これらは白人-黒人差別という枠組みに囚われている。劣等感はもとより、優越感もまたコンプレックスの裏返しに過ぎない。そこには”白人の優越性”という眼差しが残る。
差別を本質的に乗り越えるには、”黒人対白人”という構図から”人間と人間”という構図へと転換させる以外にない。それがグリフィンとファノンがともに行き着いた答えだった。奇しくも両者の結論は一致している。
グリフィンは言う。
現実には、”我々と彼ら”とか、”私とあなた”といった二項対立は存在しないのだ。すべてを包括する”我々”、同情心とすべての人間に平等な公正を求めることで結ばれた、一つの人類というものがあるだけなのである。(中略)
文化という監獄の鍵を開けるには、そうするしかないのだ。人間に対する虐待を正当化しつづけることを許している、人種や民族の持つ固定観念という社会に蔓延する害毒を、それが中和してくれるのである。(『私のように黒い夜 』pp.302-303)
他方で、ファノンはこう結論づけている。
黒人であるこの私の欲することはただひとつ。道具に人間を支配させてはならぬこと。人間による人間の、つまり他者による私の奴隷化が永久に止むこと。彼がどこにいようが、人間を発見し人間を求めることがこの私に許されるべきこと。
二グロは存在しない。白人も同様に存在しない。(『黒い皮膚・白い仮面』p.249)
黒人-白人という二項対立を乗り越えること。それが、二人が最終的に求めたものであった。
二人が生きた時代からは到底考えられないが、2009年にはアメリカ合衆国初の黒人大統領が誕生した。また、エディ・マーフィやウィル・スミス、マイケル・ジョーダンのような黒人のスーパースターも数多く存在している。当時と比べたら、差別問題はかなり解消されつつあると言える。
しかし、差別はすべてのマイノリティにつきまとう問題である。それをなくすには、劣等性を指摘するのでも優越性を主張するのでもいけない。思想や信条、人種や民族の違いの前に、”人間と人間である”ことを認めること。それ以外に、解決策はないのだ。