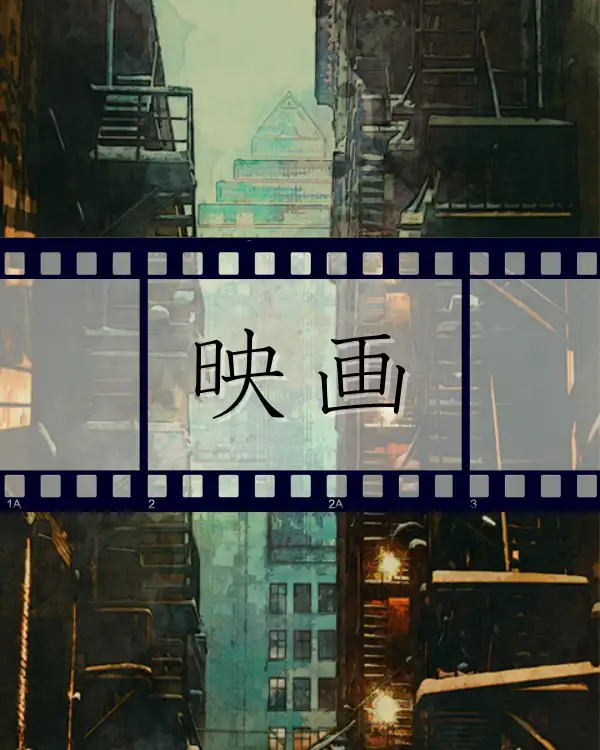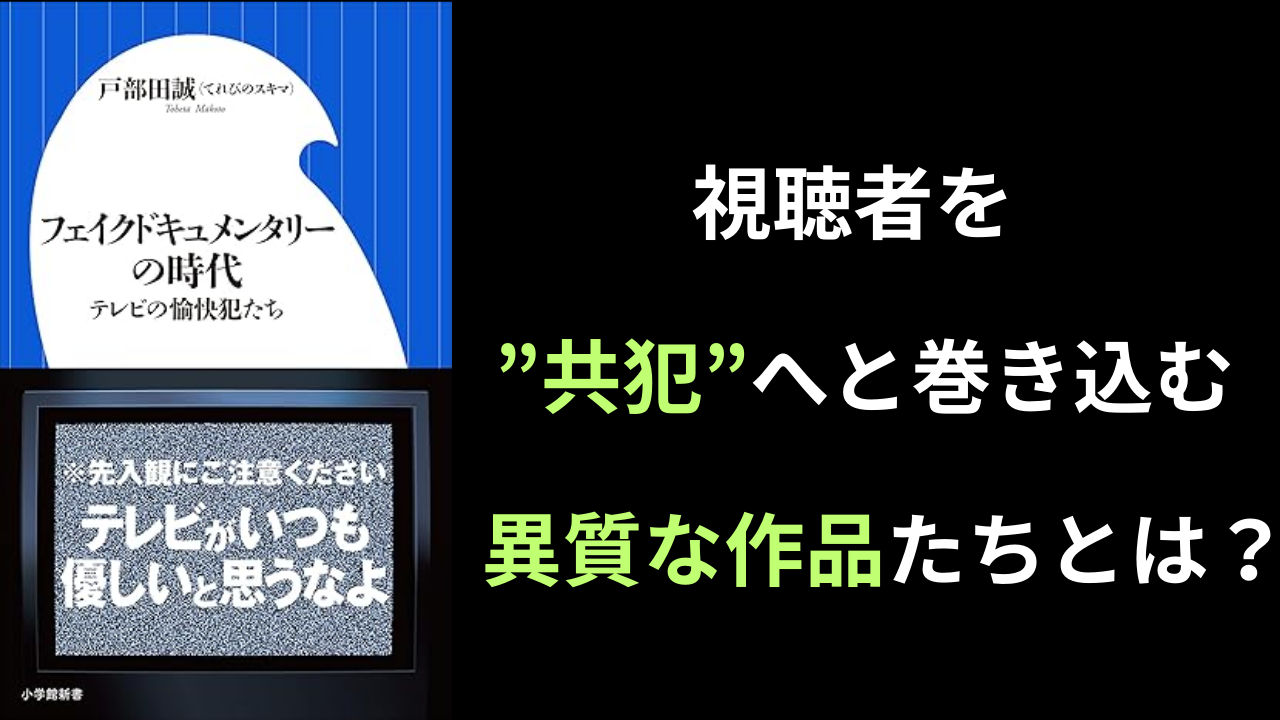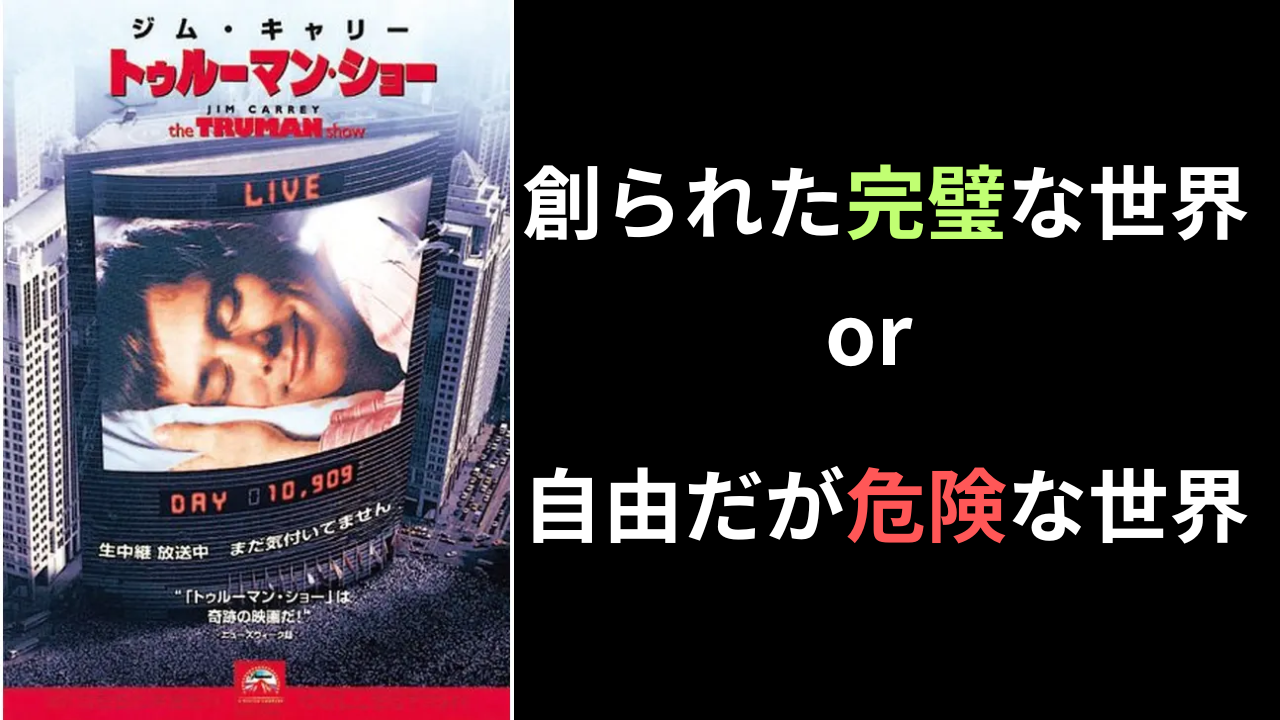世はフェイクドキュメンタリー時代
「この家、何かがおかしい」
このキャッチコピーで知られる『変な家』(雨穴)は、SNSで100万回以上読まれ、本は20万部突破、さらには映画化して大ヒットするなどとんでもない盛り上がりを見せた。
『変な家』の動画は、「特殊な間取りをしている家に違和感を抱いた雨穴氏が、その謎に迫っていく」という構成をしている。ちょっとした違和感がじわじわと恐怖に変わっていく、点と点が繋がって謎が解けていく感覚が好評を博し、再生回数は2300万回を超えている(2024年10月時点)。
このような、「本物のドキュメンタリーらしいフィクション」はフェイクドキュメンタリー(あるいは、モキュメンタリー)と呼ばれている。
フェイクドキュメンタリー自体は新しい表現形式ではない。
古くは1967年の映画『人間蒸発』(失踪した男性を追う取材過程の記録映画、というていで始まる)にその萌芽が見られる。
また、香取慎吾が女子高生二人を人質にして立てこもる事件を報道する「香取慎吾2000年1月31日」はゴールデンタイムに生放送され、「ある事情で放送禁止となったVTRを再編集し放送する」という『放送禁止』は映画化までされるほどの人気作となった。フェイクドキュメンタリーは一つのジャンルとして数十年前から存在するのである。
戸部田誠『フェイクドキュメンタリーの時代 テレビの愉快犯たち』はそんなフェイクドキュメンタリーの歴史を詳しく解説している。
昔からあるとは言えど、フェイクドキュメンタリーがニッチジャンルなことは間違いない。新作が発表されれば「あれ、フェイクドキュメンタリーらしいよ」とファンの間で話題になるくらいにはニッチだ。
この本ではテレビ史の傍流にあったフェイクドキュメンタリーについて、どのような変遷を辿ってきたのかをまとめている。私もフェイクドキュメンタリーのファンだが、「こんな昨品があったのか!」と驚かされることが多かった。今はサブスク配信サービスも充実しているため、本を片手に気になった作品を見に行くことで本書の内容を深く味わうことができた。
この本はフェイクドキュメンタリーの歴史書というだけでなく、世界を広げてくれる最高のガイドブックでもある。同ジャンルをこれだけ体系的にまとめた本は他に例がないため、今後も長く読まれる貴重な情報源となることは間違いない。
全く新しいジャンルではないにも関わらず、なぜ”今”この本が出版されたのか。
その背景にはSNSの影響でフェイクドキュメンタリーがちょっとしたブームになっていることと無関係ではないだろう。
冒頭紹介した『変な家』や「フェイクドキュメンタリー「Q」」がYouTubeで100万再生を超える他、『このテープ持ってないですか?』や『Aマッソのがんばれ奥様ッソ』などはSNSでトレンド入りし、さらにはTikTokで切り抜き動画がバズるなど大きな話題を呼んでいる。

では、なぜ”今”フェイクドキュメンタリーが流行るのか?
それは、フェイクドキュメンタリーが”不在”と”共犯”の作品だからである。
探偵不在のミステリ、ツッコミ不在のお笑い。
フェイクドキュメンタリーは、「フィクションを真実らしく語る」という形式を取る。
例えば、『変な家』は架空の間取り図をあたかも本物のように扱うってその謎を追う。
『Aマッソのがんばれ奥様ッソ』では(明らかな違和感がある家庭の)お宅訪問を行う。
お笑いバラエティ『ぜんぶウソ』はオードリーやサンドウイッチマンといったお笑い芸人を使いながらも、ドキュメンタリーの体を守っている。
「事実を追いかけて映す」のがドキュメンタリーである以上、それらをメタ的に批評する人物は作品内に出てこない。
「そんなわけないだろ!」とその枠組み自体を否定してしまったら台無しになってしまうからだ。
視聴者に向けて謎を解説する人はいないし、シュールな光景にツッコむ人もいない。
違和感ある映像だけを見せ、その解釈は視聴者に委ねる。
それがフェイクドキュメンタリーなのだ。
先ほど触れた『Aマッソのがんばれ奥様ッソ』の公式番組紹介は以下のようになっている。
コンビ揃って結婚していたことが報じられたAマッソのBSテレ東での初冠番組「Aマッソのがんばれ奥様ッソ」!芸能界のおせっかい奥様が日頃大変な思いをしている奥様たちのお悩み解決に大奮闘!笑いあり、涙ありのハートウォーミングバラエティです!
(TVer番組紹介『Aマッソのがんばれ奥様ッソ』)
もちろん、ここではフェイクであることを一切表に出さない。ひと山いくらのバラエティに擬態している。
番組は一見普通のお宅訪問番組のように進んでいく。だが、その中には随所に違和感が散りばめられているのだ。
第一話では血の繋がっていない父娘が登場し、娘が「お父さんみたいな人と結婚したい」と発言する。
ここまでなら「子どもの言うことだし」で済むが、父親を「翔は…」と呼び捨てにしてしまう、母親を敵視する言動などが重なると不穏さを隠せなくなってくる。
だが、不貞を匂わす描写を入れつつも、それには触れないまま番組は終わる。
それを見た視聴者が「あれってこういう意味だよね?」と小さな違和感の答えを探るのがフェイクドキュメンタリーの醍醐味なのである。
『奥様ッソ』はミステリ的なフォーマットだが、フェイクドキュメンタリーにはお笑いもある。
もう一つ、『ぜんぶウソ』というお笑いフェイクドキュメンタリーも紹介しよう。

『ぜんぶウソ』は2009年に放送された、お笑い芸人たちが役を演じる一話完結型のフェイクドキュメンタリーである。ここでは第一回の「家出少女 神と呼ばれる男~米倉徹の挑戦~」を取り上げる。
この回は矢口真里がレンタルDVDショップで借りてきたDVDを自室で再生するシーンから始まる。そのDVDの内容は「泊めてくれる人を探す家出少女(通称:”神待ち”)を積極的に家に泊めている”米倉徹”という男への密着ドキュメンタリー」である。視聴者はワイプで抜かれている矢口と一緒にこの番組を視聴することになる。
この番組ではオードリー春日扮する米倉が「100%善意で少女を泊めている慈愛の人」と紹介され、彼は善良な市民として扱われる。
しかし、視聴者からしたらツッコミどころ満載。
全体を通して見ると、「下心のある気弱な男が利用され、最後には家を追い出されて公園生活をするはめになる」というコントになっている。
だが、通常のコントと違うのは、ツッコミ役がいないところである。矢口の「えぇつ!」といった反応はありつつも、過度なツッコミや笑い声の効果音などは一切ない。終始真面目なドキュメンタリーの体裁を崩さないのだ。
こうした例を見るとわかるように、フェイクドキュメンタリーは探偵不在のミステリ、ツッコミ不在のお笑いなのである。
探偵役もツッコミ役も、読者を安心させる役割がある。
謎があるまま終わったら、おかしさが指摘されないまま終わったらモヤモヤとした不安が残ってしまう。
だが、探偵役が謎をわかりやすく解説し、ツッコミ役が違和感を短いフレーズで表せば、視聴者はスッキリとした気持ちで作品から離れられる。
「わかりやすい」とは「安心できる」ことだからだ。
ただ、フェイクドキュメンタリーにおいてわかりやすい説明は野暮である。少なくとも作り手にその意識があるのは間違いない。
『奥様ッソ』を生んだ大森時生は、放送当時の反響についてこう振り返っている。
大森の思惑通り話題になった『奥様ッソ』だが、ひとつ”誤算”もあった。『奥様ッソ』は自身が初めて演出する作品だったため「何がなんでも視聴者に見つかろう」という”下心”があり、自分の趣向を抑えてかなりわかりやすく演出した。その結果、SNS等では「わかりやすすぎる」という声が上がったのだ。それを見て「次からは自分の好みの雰囲気をもうちょっと押し出してもいいのかもな、と背中を押された」感じがあったという。
(『フェイクドキュメンタリーの時代 テレビの愉快犯たち』p.278)
大森は視聴者に見つかるためにわかりやすく演出したが、本当はそんな野暮なことはしたくなかったのだろう。
しかし、わけのわからない作品となってしまったらそもそも話題にならない。
だからこそ自分の趣味を抑え、わかりやすい演出を選んだのである。
その結果、見え見えのツッコミどころが人々の言及を呼び、XやTikTokのバイラルを生んだことを思うと、この戦略は成功だったと言える。
違和感の解説者は作品内に存在しない。
それでいてわかりやすくもしない。
では、誰が違和感を氷解する役目を担うのか?
他ならぬ視聴者自身である。
フェイクドキュメンタリーの本質とは、受け手が共犯者となる”遊び”である。
フェイクドキュメンタリーの作品名で検索すると気がつくことがある。
それは、「作品名+考察」が検索候補に上がることだ。

フェイクドキュメンタリーの多くは解説を放棄している。「わかったよね?」という信頼関係のもと、解釈を視聴者に委ねる。
だが、”わからなさ”を抱えたままでは、視聴者は日常に帰れない。なんとも言えない気持ち悪さ、もどかしさが残り続けてしまう。
わかるまで考えるか、他の視聴者の考察を探しにいかざるをえないのだ。
作者は”わかりにくい”作品を提示し、視聴者はそれを自分で解釈する。あるいは他人の考察を見て理解する。
このような作品と視聴者との”共犯”によってフェイクドキュメンタリーは成立する。
『フェイクドキュメンタリーの時代』の著者、戸部田誠はフェイクドキュメンタリーの共犯性についてこう語る。
フェイクドキュメンタリーにおける「フェイク」は作り手の受け手である視聴者に対する「信頼」の証明に違いない。「この遊びに付き合ってくれますよね?”共犯関係”になってくれますよね?」とフェイクを仕掛ける。その申し合わせを受け取った視聴者は、限られた情報をもとに自分たちの想像力と探究心でそこから”真実”を導き出そうと模索する。それこそが、作り手と受け手の幸福な関係性ではないか。
(『フェイクドキュメンタリーの時代 テレビの愉快犯たち』p.310)
フェイクドキュメンタリーの本質とは、作り手と受け手とが共犯関係になり、受け手が”真実”を導き出そうと模索するという”遊び”である。
遊びである以上、受け手である視聴者も参加しなければいけない。
フェイクドキュメンタリーが今これだけ流行っているのも、SNSの登場によって遊びへ参加するステージが増えたことと無関係ではない。
ブログ、X、YouTubeなど、あらゆる媒体で作品が考察されており、考察を見る側もする側もそれらを楽しんでいる。
遊びやすくなったことで、作品自体の体験価値が上がっているのである。
ただ、多くの人はそこまで真剣に”遊ば”ないだろう。
「さっさと考察を見て納得してしまいたい」とさっさと消費するだけのことがよほど多いと思う。
しかし、作品で真剣に遊べば、それは他の作品では得られない体験となる。
2002年に発表された『ひぐらしのなく頃に』は、考察という名の遊びに大勢を巻き込んだ最たる例である。
作品が人生に干渉したとき、物語は「私の物語」になる。

「オヤシロ様の祟り」と呼ばれる連続怪死事件が起きる雛見沢村を舞台としたこの作品は、「出題編」と「解答編」に分かれて発表された。出題編は四つの物語から成るが、それぞれが別種の謎を持ったミステリとなっている。
一連の事件の黒幕は誰なのか、どうやって事件は受けているのか、そもそもオヤシロ様の祟りは本当にあるのか…。「惨劇に挑め。」という挑発的なキャッチコピーとともに多くの謎を残したこの作品に、当時の考察民は熱中した。出題編が出てから解答編が出るまでの数年の間、ブログや2chには考察や議論掲示板が乱立することとなった。中にはブログに書いていた考察が出版された人までいる。
そこまでくると考察はただの感想文などではない。
もはや自己表現とコミュニケーションの場である。
『ひぐらしのなく頃に』が完結してから数年後に『ひぐらしのなく頃に 業』という完全新作が発表されたが、そのときに作者の竜騎士07は『ひぐらし』と考察について次のように語っている。
――(中略)現在、『ひぐらし業』の全24話が放送され、第1話からSNSを通じてさまざまな考察で盛り上がっています。視聴者のリアクションに関してはどう受け止めていますか?
竜騎士07 私としては、いちばん理想的な楽しみ方をしてもらっているなと感じています。TVアニメ『ひぐらしのなく頃に(以下、平成版ひぐらし)』が放送されたのは2006年なので、当時はSNSで気軽につぶやけるような環境は整っておらず、限られた掲示板などで議論するしかなかったんですよね。今はすごくカジュアルに意見交換ができる時代になって、理想的だなと思います。――たしかにコアなファンから初見の人まで、幅広い層が考察を楽しんでいますね。
竜騎士07 それは本当にうれしいことです。もともと『ひぐらし』は犯人やトリックを暴くことを目的とした「正統派ミステリー」というより、考察そのものを楽しんでもらいたいと思って作った作品なんです。ただ、最初に発表した際にはそういう土壌が醸成されておらず、犯人当てゲームの一環として受け止められて、犯人を当てた人がスゴくて、それ以外は認めないという雰囲気があったんです。私としては、正解不正解というよりも、みんなで意見を交換して話し合う、その体験そのものに価値があって楽しいものだと思っています。私にとって『ひぐらし』シリーズは「考察遊びの場」であり、一種のコミュニケーションゲームだとも思っているんです。
(Febri「ひぐらしのなく頃に業 原作・竜騎士07インタビュー」)
『ひぐらし』シリーズは「考察遊びの場」であり、一種のコミュニケーションのゲームだとまで作者は語っている。
作品―視聴者という関係だけでなく、作品を媒介とした視聴者―視聴者という関係が構築されることを意図しているのである(これについて竜騎士07もまた”遊び”という表現を使っていることも興味深い)。
ただ物語を見たままに消費して終わりではなく、自分なりの解釈を出そうと頭を捻り、そして考察を通じて他者とコミュニケーションする。
色んな考察を読み漁る、自分も考察を書いてみようとブログを立ち上げる、Xで勇気を出して発信してみる、友人と「あの考察見た?」と会話する。
このように作品が人生に干渉する経験を経ることで「与えられただけの物語」は「私の物語」へと昇華されるのだ。
『ひぐらし』を例に挙げたが、フェイクドキュメンタリーというジャンルはそれ自体が視聴体験の拡張性を内包している。作品を見るだけに留まらず、考察を探す、考察をする、そして考察を巡って交流するといったメタ的体験が生まれやすい性質を持っているのだ。
SNSが全盛のこの時代、どんな作品も「語られる」ことを意識せずに創作はできない。
これからのフェイクドキュメンタリーは「語られ方」までデザインされた作品が増えていくことだろう。